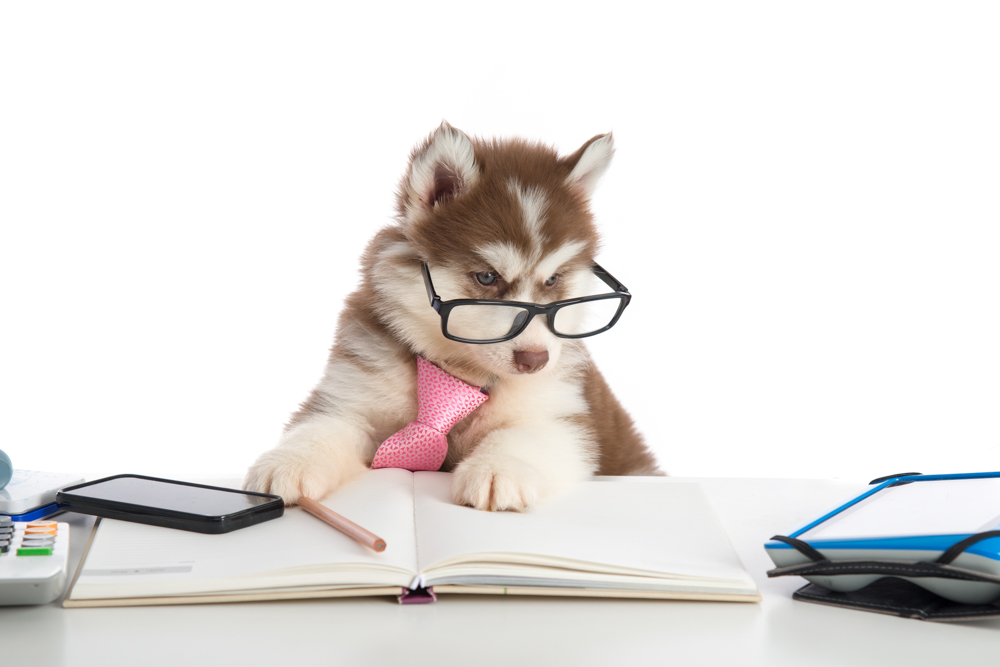日本には、四季折々の自然と調和しながら受け継がれてきた、さまざまな仏教行事があります。これらの行事は、仏教の教えを実践し、ご先祖や仏様に感謝を捧げる大切な機会です。家族でお寺を訪れたり、自宅で手を合わせたりすることで、日常の喧騒から離れ、心を静める時間を持つことができます。
このページでは、代表的な仏教行事を一年間のスケジュールに沿ってご紹介します。それぞれの行事の意味や由来を知ることで、仏教に込められた教えや、日本の伝統文化に対する理解を深めるきっかけになることでしょう。ぜひ、ご家族や大切な方とともに、仏教行事に親しみ、心豊かな時間をお過ごしください。
🌸 春の行事
- 2月15日:涅槃会(ねはんえ)
- お釈迦様が入滅(亡くなった日)を偲ぶ行事。
- 涅槃図(お釈迦様が横たわる姿を描いた図)を掲げて供養。
- 3月(春分の日を中心とした1週間):春彼岸(はるひがん)
- 先祖供養を行う期間。「お墓参り」や「お彼岸法要」が行われる。
- 春分の日は「自然に感謝し、ご先祖を敬う日」として定められている。
- 4月8日:花まつり(灌仏会)
- お釈迦様の誕生を祝う行事。
🌻 夏の行事
- 7月~8月(地域により異なる):お盆
- 先祖の霊を迎え、供養する仏教最大の行事。
- 「迎え火」「送り火」「精霊流し」などの風習が地域ごとにある。
- 7月15日または8月15日:盂蘭盆会(うらぼんえ)
- お釈迦様が弟子に「供養を通じて先祖の苦しみを救える」と説いた教えに由来。
- お盆の中心的な法要。
🍁 秋の行事
- 9月(秋分の日を中心とした1週間):秋彼岸(あきひがん)
- 春彼岸と同じく、先祖供養を行う。
- 「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるように、季節の節目にあたる。
❄️ 冬の行事
- 12月8日:成道会(じょうどうえ)
- お釈迦様が悟りを開いた日を祝う。
- 寺院では「座禅」や「読経」などの修行体験を行うところもある。
- 12月31日:除夜の鐘
- 大晦日の夜に108回の鐘を突いて「煩悩を払う」行事。
- 新年を迎えると同時に心を清める。